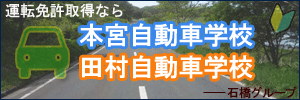トップ登場
「菜の花を植えて大地を救う」 環境運動のパイオニア 藤井絢子さん

菜の花プロジェクトネットワーク代表 藤井絢子さん
【略歴】1946(昭和21)年、横浜市生まれ。上智大文学部卒。滋賀県守山市在住。滋賀県環境生活組合理事長、環境省中央環境審議会臨時委員、リサイクルせっけん協会長、バイオマス活用推進専門家会議委員、自治体学会運営委員、日本環境会議理事、日本グランドワーク評議員、全国バイオディーゼル燃料利用推進協議会副会長。著書に「菜の花エコ革命」「菜の花エコ事典」「チェルノブイリの菜の花畑から」(いずれも創森社から出版)がある。
【略歴】1946(昭和21)年、横浜市生まれ。上智大文学部卒。滋賀県守山市在住。滋賀県環境生活組合理事長、環境省中央環境審議会臨時委員、リサイクルせっけん協会長、バイオマス活用推進専門家会議委員、自治体学会運営委員、日本環境会議理事、日本グランドワーク評議員、全国バイオディーゼル燃料利用推進協議会副会長。著書に「菜の花エコ革命」「菜の花エコ事典」「チェルノブイリの菜の花畑から」(いずれも創森社から出版)がある。
琵琶湖の赤潮化がきっかけとなり、汚染原因となった廃食油を回収して石けんをつくる廃食油リサイクル運動が20数年前、滋賀県から始まった。市民運動はナチュラルな石けんづくりに始まり、脱化石代替燃料のバイオディーゼル燃料の生産、農業再生の取り組みへと進んでいく。こうした環境運動を実現する「菜の花プロジェクト」も各地に立ち上がり、全国に広がっていった。休耕田や耕作放棄地の有効活用、代替エネルギー源としての役割を果たしてきたナタネ栽培だが、チェルノブイリ原発、福島原発の事故を機に、放射能汚染土壌の改良という新たな役目が加わった。ナタネの除染効果は、農林水産省によって実証研究の段階だが、放射性セシウムやストロンチウムを吸着する性質を持つとされる。琵琶湖の環境運動で先駆的役割を果たし、再生可能(自然)エネルギーの普及にも取り組む「菜の花プロジェクトネットワーク」代表の藤井絢子(あやこ)さんに、環境への取り組みと、福島再生の思いを聞いた。
-環境問題とのかかわりは。
「1977年、琵琶湖が富栄養化による赤潮に直面したのがきっかけだった。今までの日本の公害問題は四日市や水俣にみられるように、『企業が悪い』と企業にもの申すことだった。琵琶湖の水が汚れた、まずくなった水ということでは私たちが被害者ではあるが、同時に水源地や周りに住む私たちが汚した側、つまり加害者性を感じたことでもあった。そこで市民も主体的に動くことがないと、琵琶湖(の問題)には向えないと考えた。そうした運動の長い歴史の中で、典型的なのが『せっけん運動』。暮らしの中で私たちがどういうことを変えていけば、富栄養化を少しでも減らすことができるか。それまで何も考えずにリンの入った合成洗剤を使う暮らしからナチュラルな石けんに変えることで、琵琶湖に富栄養化の現象が進むことをストップしたいというのが70年代の運動だった」
-琵琶湖の水質保全でどうような活動を。
「当時、私が琵琶湖にいてよかったと思うのは、滋賀県知事が武村正義さん(後の衆院議員、大蔵大臣)だったこと。武村さんは、市民が動いたこと、感じていることをどう県の施策に乗せていけばいいのか、今でいう自治のその形を探っていた知事だった。行政と市民がいい両輪で動いた時に、環境問題に一つの回答を出せるというように、逆に私たちも武村さんから学んだ。『せっけん運動』をやっていく中で、一時はリンが少なくなり、琵琶湖の状態が良くなったかに見えたが、実は深いところで進行し、赤潮から80年代にはアオコまで出てくるようになった。運動を持続するのは難しいもので、『せっけん運動』も後退していく中、もう一度、琵琶湖に向き合おうと考えた。何が汚している原因かを探ってみようと、川の源流から琵琶湖まで歩いてみた。そこで見つけたのが、琵琶湖の水源地が汚染され、水をきれいにする仕組みが周辺にできていないことだった。生活雑排水から農業汚水、産業現場のものも入り込み、ダイレクトに琵琶湖にこうしたものが入ってくるのを見た時、これは大変だと思った。水をきれいにする仕組みを調べていけば、都会型の大がかりな下水処理施設できれいにしてしまおうという話ばかり。地方にはとても合わなかった。そこで、地域にあった水処理として合併処理浄化槽を提案し、設置を展開していった」
-菜の花プロジェクトの母体となった自然エネルギーへの取り組みは。
「90年代になると温暖化問題など難しい課題が出て、琵琶湖においても大きな問題となってぶち当たった。私たちはナチュラルな石けんを作る原料として、廃食油を回収する仕組みを作っていたため、バイオディーゼル燃料への取り組みを重ねていった。化石燃料に代わるのもとして始めた中で、ヒントをくれたのがドイツだった。使い終わった廃食油でバイオディーゼル燃料に挑戦しよういうのが、環境問題への第2弾だった。第1弾が水環境再生、そして再生可能(自然)エネルギーの取り組みに入っていった。3弾目は耕作放棄地が進む中での農業現場の問題だった。私たち自身がどんな地域にしたいかということを議論する中で、水環境にも心を寄せる、エネルギーもこのままでは良くない、農家の現場もこれではだめ。このすべてをつないでいく循環の仕組みを伝えていく中で、わかりやすくて、楽しくて、わくわくするような仕掛けがほしいと考えた。これに、<菜の花プロジェクト>という名前を付け、98年からはこれを前面に、資源循環、食とエネルギーの自立の構造をつくっていった。あとは関心を持つ地域がどんどん立ち上がっていった。(各団体が)先進地を視察し、そうした中から菜の花プロジェクトが一定の広がりをもっていった」
-福島原発事故が起こり、大地や海が汚染されてしまった。今後はどのような活動を。
「菜の花プロジェクトが全国に展開する中で、海外でも菜の花プロジェクトをやっている国があった。モンゴル、韓国、中国、そして2006年からチェルノブイリでも始まっていた。昨年はチェルノブイリ原発事故25周年。行こうとした矢先に大震災があり、福島原発事故が起きた。そうした状況の中で、農地の再生と放射性物質がどうなっているかをきっちりと聞いてこないといけないと考え、同時に福島での問題も併せ持ちながらやってきた」
-国産バイオ燃料への期待は。
「02年から着目されて動き始めたが、この何年かはエタノールの方に重点が置かれているきらいがある。このBDF(バイオディーゼル燃料)の場合は規模ではなくて、各地域にそれぞれに合ったサイズで動いていることでは、ポイントとしては多いと思う。各地で動いていることが大事で、そういう意味でバイオ燃料はもっと評価されなければならないと思う。使っている側は、相当数のクオリティーと地域の連携軸をつくらなければならない。まさに連携の中の燃料であり、中東から持ってくるのとはまったく違う、地域の仕組みとクオリティーを追求したバイオ燃料であってほしいと思う。何よりも自分たちの地域にエネルギーになるものがあるのだということを、住民たちが知ることが大事」
-休耕田の有効活用や地球温暖化防止、自然エネルギー推進などを掲げた菜の花プロジェクト活動に、放射能汚染土壌の浄化という役目が加わり、存在がより重要となってきているが。
「今までのメディアの取り上げ方では、土壌の吸着能力は?、何%吸着ですか、という言われ方が多く、3%程度と書かれてしまっていることが多かった。ところがチェルノブイリでわかったことがある。(放射性物質は)1年目は菜種で吸着させ、その菜種油をバイオ燃料で使う。翌年は食べ物となるものを作る。3年目は家畜の飼料を作る。そして4年目でまた吸着させるというサイクルを繰り返す。それは吸わせる能力を超えて、農地を有効に使えるのだという大きな発見だった。この3年輪作により、農地が有効に使えることを突き止めたことが非常に大きい」
-東北の被災県、放射能汚染、風評被害に苦しむ福島県へのアドバイスと応援メッセージを。
「被災地が持っている問題は、実は日本が遠からずそういう地域になってしまうということでもある。高齢化や、耕作放棄地がどんどん出てくるということは、そういう局面に入っていて、表舞台にあぶり出したことでもある。福島の再生は、日本の再生につながると強く言いたい。むしろ私たちは被災地のためにというよりも、実は日本の再生はここ福島にかかっている。深いところで私たち自身の、日本自体の将来が危うくなっている。再生プログラムに性根を入れて、ともに新たな日本をつくるためにこの福島から始めましょう」
(2012・5・31)
-環境問題とのかかわりは。
「1977年、琵琶湖が富栄養化による赤潮に直面したのがきっかけだった。今までの日本の公害問題は四日市や水俣にみられるように、『企業が悪い』と企業にもの申すことだった。琵琶湖の水が汚れた、まずくなった水ということでは私たちが被害者ではあるが、同時に水源地や周りに住む私たちが汚した側、つまり加害者性を感じたことでもあった。そこで市民も主体的に動くことがないと、琵琶湖(の問題)には向えないと考えた。そうした運動の長い歴史の中で、典型的なのが『せっけん運動』。暮らしの中で私たちがどういうことを変えていけば、富栄養化を少しでも減らすことができるか。それまで何も考えずにリンの入った合成洗剤を使う暮らしからナチュラルな石けんに変えることで、琵琶湖に富栄養化の現象が進むことをストップしたいというのが70年代の運動だった」
-琵琶湖の水質保全でどうような活動を。
「当時、私が琵琶湖にいてよかったと思うのは、滋賀県知事が武村正義さん(後の衆院議員、大蔵大臣)だったこと。武村さんは、市民が動いたこと、感じていることをどう県の施策に乗せていけばいいのか、今でいう自治のその形を探っていた知事だった。行政と市民がいい両輪で動いた時に、環境問題に一つの回答を出せるというように、逆に私たちも武村さんから学んだ。『せっけん運動』をやっていく中で、一時はリンが少なくなり、琵琶湖の状態が良くなったかに見えたが、実は深いところで進行し、赤潮から80年代にはアオコまで出てくるようになった。運動を持続するのは難しいもので、『せっけん運動』も後退していく中、もう一度、琵琶湖に向き合おうと考えた。何が汚している原因かを探ってみようと、川の源流から琵琶湖まで歩いてみた。そこで見つけたのが、琵琶湖の水源地が汚染され、水をきれいにする仕組みが周辺にできていないことだった。生活雑排水から農業汚水、産業現場のものも入り込み、ダイレクトに琵琶湖にこうしたものが入ってくるのを見た時、これは大変だと思った。水をきれいにする仕組みを調べていけば、都会型の大がかりな下水処理施設できれいにしてしまおうという話ばかり。地方にはとても合わなかった。そこで、地域にあった水処理として合併処理浄化槽を提案し、設置を展開していった」
-菜の花プロジェクトの母体となった自然エネルギーへの取り組みは。
「90年代になると温暖化問題など難しい課題が出て、琵琶湖においても大きな問題となってぶち当たった。私たちはナチュラルな石けんを作る原料として、廃食油を回収する仕組みを作っていたため、バイオディーゼル燃料への取り組みを重ねていった。化石燃料に代わるのもとして始めた中で、ヒントをくれたのがドイツだった。使い終わった廃食油でバイオディーゼル燃料に挑戦しよういうのが、環境問題への第2弾だった。第1弾が水環境再生、そして再生可能(自然)エネルギーの取り組みに入っていった。3弾目は耕作放棄地が進む中での農業現場の問題だった。私たち自身がどんな地域にしたいかということを議論する中で、水環境にも心を寄せる、エネルギーもこのままでは良くない、農家の現場もこれではだめ。このすべてをつないでいく循環の仕組みを伝えていく中で、わかりやすくて、楽しくて、わくわくするような仕掛けがほしいと考えた。これに、<菜の花プロジェクト>という名前を付け、98年からはこれを前面に、資源循環、食とエネルギーの自立の構造をつくっていった。あとは関心を持つ地域がどんどん立ち上がっていった。(各団体が)先進地を視察し、そうした中から菜の花プロジェクトが一定の広がりをもっていった」
-福島原発事故が起こり、大地や海が汚染されてしまった。今後はどのような活動を。
「菜の花プロジェクトが全国に展開する中で、海外でも菜の花プロジェクトをやっている国があった。モンゴル、韓国、中国、そして2006年からチェルノブイリでも始まっていた。昨年はチェルノブイリ原発事故25周年。行こうとした矢先に大震災があり、福島原発事故が起きた。そうした状況の中で、農地の再生と放射性物質がどうなっているかをきっちりと聞いてこないといけないと考え、同時に福島での問題も併せ持ちながらやってきた」
-国産バイオ燃料への期待は。
「02年から着目されて動き始めたが、この何年かはエタノールの方に重点が置かれているきらいがある。このBDF(バイオディーゼル燃料)の場合は規模ではなくて、各地域にそれぞれに合ったサイズで動いていることでは、ポイントとしては多いと思う。各地で動いていることが大事で、そういう意味でバイオ燃料はもっと評価されなければならないと思う。使っている側は、相当数のクオリティーと地域の連携軸をつくらなければならない。まさに連携の中の燃料であり、中東から持ってくるのとはまったく違う、地域の仕組みとクオリティーを追求したバイオ燃料であってほしいと思う。何よりも自分たちの地域にエネルギーになるものがあるのだということを、住民たちが知ることが大事」
-休耕田の有効活用や地球温暖化防止、自然エネルギー推進などを掲げた菜の花プロジェクト活動に、放射能汚染土壌の浄化という役目が加わり、存在がより重要となってきているが。
「今までのメディアの取り上げ方では、土壌の吸着能力は?、何%吸着ですか、という言われ方が多く、3%程度と書かれてしまっていることが多かった。ところがチェルノブイリでわかったことがある。(放射性物質は)1年目は菜種で吸着させ、その菜種油をバイオ燃料で使う。翌年は食べ物となるものを作る。3年目は家畜の飼料を作る。そして4年目でまた吸着させるというサイクルを繰り返す。それは吸わせる能力を超えて、農地を有効に使えるのだという大きな発見だった。この3年輪作により、農地が有効に使えることを突き止めたことが非常に大きい」
-東北の被災県、放射能汚染、風評被害に苦しむ福島県へのアドバイスと応援メッセージを。
「被災地が持っている問題は、実は日本が遠からずそういう地域になってしまうということでもある。高齢化や、耕作放棄地がどんどん出てくるということは、そういう局面に入っていて、表舞台にあぶり出したことでもある。福島の再生は、日本の再生につながると強く言いたい。むしろ私たちは被災地のためにというよりも、実は日本の再生はここ福島にかかっている。深いところで私たち自身の、日本自体の将来が危うくなっている。再生プログラムに性根を入れて、ともに新たな日本をつくるためにこの福島から始めましょう」
(2012・5・31)
おすすめ情報(PR)
 |
既製服にはない美しいフィット感 誂えのセレクトショップ・佐藤洋服店(本宮市)は、既製服にはないフィット感の美しいシルエットのスーツなどを提供している。ジャケット、オーダースーツ、靴なども取り扱っている。 |
 |
海産物専門店「おのざき」の通販 全国一律1,000円の送料。届け先1件あたり。クール代・税込み。お買い上げ代金10,000円以上で送料無料。フリーダイヤル0120-024-137。携帯電話からは0246-23-4174 |
 |
日持ちする「プリザーブドローズ」 にこにこバラ園(須賀川市)は、1年以上持つというプリザーブドローズを発売。バラ園がデザインしたプリザのバラアレンジメント。バラの季節を迎え、特価でのバケツ売りの特売日もあり。ホームページ2,000円〜10,000円台(消費税別)。送料は別途。Tel・Fax0248-72-7834 |
 |
かに徳の宴会と法要プラン かに刺し満足コース・かにすき鍋満足コース・かにちり鍋満足コースを用意。2時間飲み放題。無料送迎バス付き(10名様以上)。予約は☎024-931-2188 |
 |
亀屋食品こだわり豆腐ギフトセット 木綿青ばた豆腐、青ばた寄せ豆腐、ごま豆腐、手あげなどの1500円セット(7品6種)と2000円セット(10品7種)。箱代・氷代込み。送料は別途。電話0248-82-2760・ファックス0248-82-2761 |
 |
本宮特産・本宮烏骨鶏の酵母卵 ビール酵母で元気に育った烏骨鶏の酵母卵とトローリ酵母卵。熱処理した高品質の飼料をエサに安心・安全に飼育しました。卵黄のみを使って独自開発した酵母卵の卵油もどうぞ。 |
 |
潮目食堂エブリア店オープン 海産物専門のおのざき(いわき市平鎌田町)は、いわき市鹿島の鹿島ショッピングセンターエブリア内に潮目食堂をオープン。2店目。ボリュームのある海鮮が自慢で、海鮮丼、刺身盛り、焼き魚定食など豊富なメニューを用意。 |
 |
縫製工場・店舗が営業再開 台風19号による水害で縫製工場・店舗が被災した(株)アルバTOWA(旧東和ユニフォーム・本宮市本宮字舘町2-1)、SATO TAILOR 佐藤洋服店(同)は、ともに営業を再開 |
おすすめサイト
- アシストパーク郡山(市民活動サポートセンター)
- まざっせプラザ
- 目崎雅昭オフィシャルサイト
- 玄侑宗久 公式サイト
- 東日本大震災中央子ども支援センター 福島窓口
- たまきはる福島基金
- NHK文化センター郡山教室
- 第1回「ふくしまを謳(うた)い写そう~桜フォトコンテスト」応募写真
- 第一回「ふくしまを謳い 写そう桜フォトコンテスト」入賞者決まる
- ホームページ制作MEGATONET
- 佐藤玲奈ホームページ
- 明成エンジニアリング
- 郡山市整骨院けんしん
- 福島県マンション管理会社ならタイテン
- 福島県郡山市訪問マッサージ
- 賃貸マンション 郡山市大槻町【大槻矢野目マンション】
- カーライフ福島郡山店
- アンティークコイン販売 タイテン
- ポポハウスうさぎの杜